社員インタビュー個人投資家の皆様へ
- ホーム
- 個人投資家の皆様へ
- 社員インタビュー一覧
- 社員インタビュー
対談メンバー

持続可能な成長を目指して――
MELの内部成長戦略とサステナビリティの最前線
1. 内部成長の強さ、稼働率の高さなど運用面における強み

H.I
まずは内部成長について教えてください。毎期継続して比較的高い増額率の賃料増額が達成できています。また、稼働率も安定しており、このような稼働の安定性や賃料増額の継続性について、投資家の皆さんからも高くご評価をいただいております。この背景について教えてください。
K.A
まず、需要面ではECの拡大、配送の効率化、雇用確保等を背景に、大型、ハイスペック、好立地の物流施設の需要が高いです。
それに伴い供給も増えていますが、新規で開発される案件は建築費高騰等の影響も受け、賃料が高く、リースアップも以前とは異なり、1~2年程度の時間がかかるケースも散見されます。このような新規の物件と既存の物件とで賃料ギャップがあり、それを埋める形で賃料増額が続いています。
MELの保有している物件についてはテナント様のニーズを満たす物件が多く、上場来非常に高い稼働率を維持しつつ、5%を超える水準での増額改定が実現できています。高い水準で増額改定が実現できている事例も多くあります。

- H.I
- 最近では金利上昇やインフレなどの影響も懸念されていますが、これらへの対応も重要ですよね。
- K.A
- そうですね。マーケット水準までの賃料増額をめざすことはもちろん、テナント様の満足度を高める施策を実施することにより収益向上ができるように取り組んでいます。また、物価上昇やマーケット動向などをふまえ、あえて短い契約の締結を目指すケースもあります。また、比較的長期の契約ではCPI連動条項などを契約に入れることで物価上昇対応をしています。
- H.I
- ありがとうございます。続いて、三菱地所グループならではの特徴や取り組みについても教えてください。
- K.A
-
MELの運用物件について、新規リーシングやテナント様との交渉などは、三菱地所を通して実施しています。三菱地所は、物流施設開発については後発組ではありますが、子会社の東京流通センターは物流事業のパイオニアであり、人材交流などを通じ、ノウハウを共有しています。
加えて三菱地所本体としても、長年のオフィスビル事業、商業施設事業の運営での経験等も活かし、物流施設のテナント様とのリレーションを構築しています。また、三菱地所の担当者は、少なくとも3か月に1回以上での頻度で各テナント様に訪問し、情報交換をしています。この訪問などを通じてテナント様の運営状況やマーケット、その他多岐にわたる情報交換を実施しています。これによってテナント様との信頼構築ができ、長期的なお付き合いにつながっていると思います。 - H.I
- 三菱地所のリレーションを活かしたリーシング事例などもありますよね
- K.A
- そうですね、オフィスでのリレーションを活かしたリーシング事例のほか、三菱地所開発のほかの物流施設でのリレーションを活かしてテナント様が決まるようなケースも複数ありますね。
2. 内部成長におけるMJIA独自施策について

H.I
また、我々資産運用会社(以下、MJIA)独自施策の取り組みについても投資家様から評価をいただくことは多いです。例えば、自家消費スキームを使用する太陽光パネルの設置や、建物固都税削減など、一つ一つは大きくないものもありますが、実績を積み重ねてきて評価は高まってきていると感じます。このあたりについても教えてください。
- K.A
-
独自施策について、収入の増加と費用の削減がありますが、まずは収入の増加についてご説明します。
LED化がされていない物件もあり、その場合は我々の負担でLED化工事を実施し、テナント様負担の電気料金を削減することができます。その一部をグリーンリース料金として我々が収受することで、双方win-winとなる施策を多数の物件にて実施しています。また、その際には単にLED化するだけでなく、調光機能、人感センサー、タイマー設定などができる高機能のものをつけて、さらに省エネ性能を高めています。(例えば、初めて実施したMJロジパーク福岡1のLED改修工事の際には、直接大阪の業者訪問するなどにより性能の高いLEDを選定し、結果としてテナント様にも喜んでいただけました。)またそのほか、倉庫内空調の設置、冷凍冷蔵倉庫の改修などもMELの負担で実施し、テナント様の満足度向上、収益性向上を実現していました。
また、太陽光パネルの設置も多くの物件で実施しています。
物流施設は屋根が広く、太陽光パネルの設置に非常に適しています。従来は太陽光パネル事業者に屋根を賃貸し、MELでは定額の収入を受領していましたが、昨今は自家消費スキームを実施することも増えてきています。
- K.M
- これらの施策は、MELの目標として定めているGHG排出量削減への寄与も大きいです。また、MELは「環境認証の取得割合を2030年度までに100%にする」という目標も打ち出しており、物件における再生エネルギー比率の向上は、その達成にも優位に働きます。このように、サステナビリティの観点でも非常に有効な取り組みであるといえます。
- K.A
- 個人的に印象に残った取り組みとしては、MJロジパーク福岡1の休憩室改修工事があります。休憩室改修にあたり、全テナント様にどのような休憩室が良いかアンケートを実施し、これをもとにデザイン会社と連携して進めていきました。印象的な壁紙などがあれば面白いのでは?と思い、私のジャストアイデアからですが、地域のデザイン専門学校生にデザインを依頼することになりました。そして集まった20作品程度を、MJIA社員やテナント様などのご意見を聞きながら決めました。時間も短い中良いものを作ることができたと思っています。テナントにとっても、地域にとっても一体感が生まれたすごく良い取り組みだったなと思います。
- K.A
-
次に、コスト削減施策についても少し説明させてください。
例えば、建物固都税の見直しを実施しています。私が私募ファンドの担当だった2005年~2006年頃からこの取り組みを実施しています。MEL全物件で建物固定資産税の検証を行っており、現在までに7物件で見直し(コスト削減)を実現しています。
また工事コスト削減の新しい取り組みとして、AI工事査定の導入も開始しました。初めての取り組みなのでまだ効果は把握できていませんが、効果については楽しみにしています。
3. サステナビリティへの取り組み
- H.I
- 続いてサステナビリティですが、MELはGHG排出量ネットゼロに向けたSBTiや環境情報開示の権威であるCDPの認定取得などを通じて外部評価機関からは高い評価を受けており、投資家様からも一定の評価をいただいていると思います。足元の取り組みについて教えてください。

K.M
まず、多くのJ-REITが参加しているGRESBリアルエステイト評価については、5年連続で最高評価である5スターを取得することができました。また、昨年からはCDPに参加しており、初参加にもかかわらず、J-REITでは数少ない最高評価であるAリストに認定されました。これらの実績は、MELがサステナビリティを積極的に推進していることを客観的に確認できる良い指標になると思います。
- H.I
- なお、現在は様々な外部評価機関が設立されており、年々評価基準も変わってきていますが、苦労したところはありますか。
- K.M
- そうですね、今は過渡期ということもあり、GRESBやCDPは毎年のように採点基準が変わってきており、それらに都度アンテナを張って対応していくことに苦労しています。また、それぞれの評価で重視されている評価基準も異なります。もちろん、それぞれの評価で高評価を取得することは大切ではありますが、最も大切なことは、幅広いサステナビリティの施策から各REITや資産運用会社が何を軸にして、何を重要視していくかということを適切に定めて推進するだと考えています。
- H.I
- 認証にとらわれず、各社で軸を定めて推進していくことが大切ということですね。サステナビリティの推進は今後も益々重要になりそうですね。
- K.M
-
三菱地所グループはサステナビリティに力を入れています。MELも環境への配慮・社会貢献・ガバナンスの強化といったサステナビリティの向上に取り組んでいくことが、社会的責務であると考えています。
また、企業価値という観点でも、これからは財務情報だけではなく、サステナビリティを含めた非財務情報が重要視されていく社会になると思っています。サステナビリティを進めることによってMEL、MJIAの企業価値向上につなげていきたいです。
終わりに
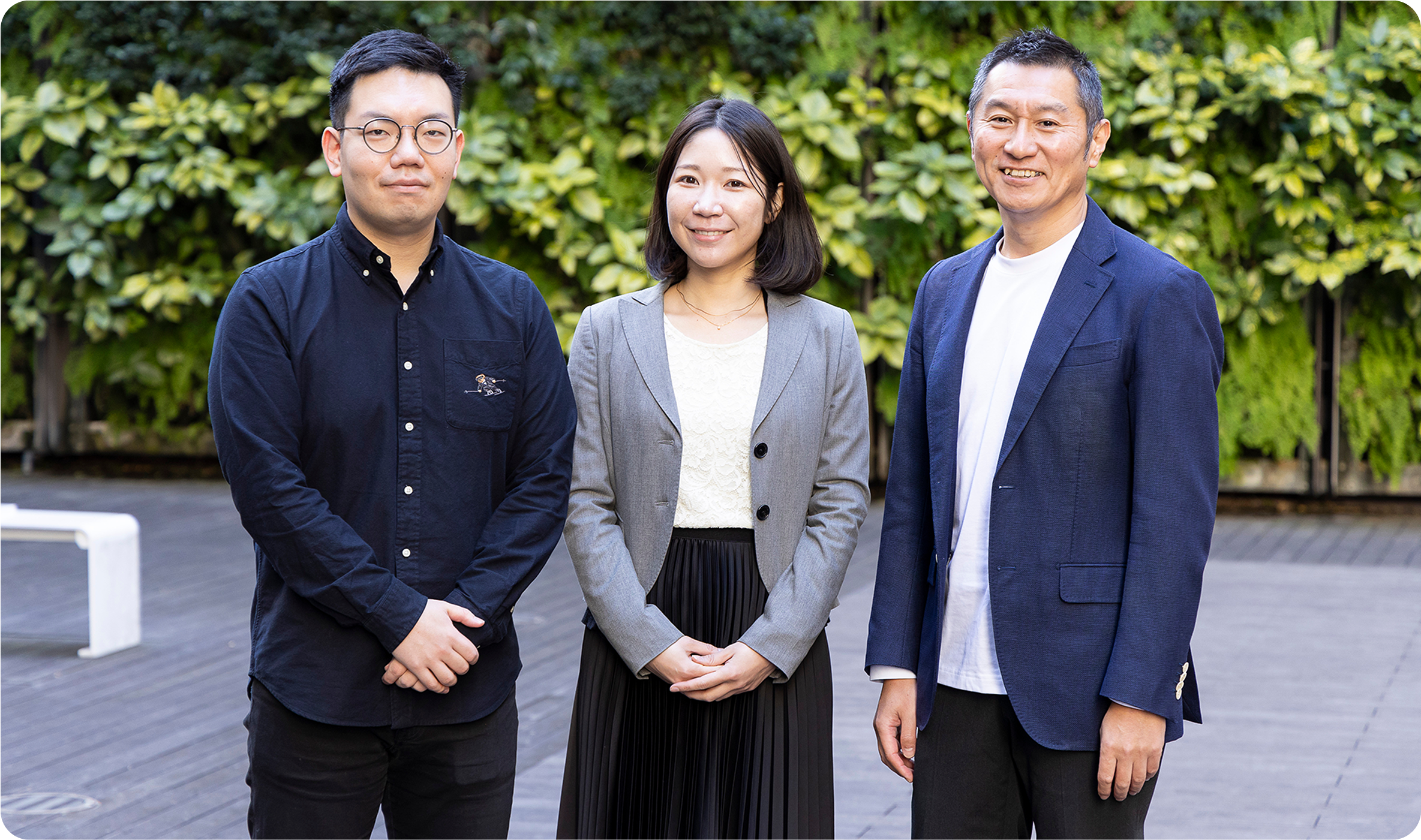
- K.A
- 普段からテナント様には「MELの施設に入居してくれてよかった」と思ってもらいたいと考えて仕事をしています。建物のスペックで満足してもらえることはもちろん、プラスαでテナント様に何かできないかということを常に考えています。これらにより、三菱地所グループ、MELのファンを増やしていきたいです。
- K.M
- 社内外へのサステナビリティの認知、啓発を強化していきたいです。サステナビリティは人々の生活に密接に関係する部分でもあり、情報開示等を通じて理解も深めていきたいです。また、基本的には中長期目線で物事に取り組み、課題を解決していきたいと考えています。
- H.I
- 内部成長の面でもサステナビリティの面でも、良い取り組みを実施できていると思っています。このようなことをしっかりと投資家様に伝えることで、MELの魅力を多くの投資家様に理解いただけるように努めていきたいです。また、投資家様とのコミュニケーション結果を社内に定期的にフィードバックすることで、より良い運営が継続できるようにしていきたいです。これらが投資口価格向上にも繋がればと思っています。
(2025年1月実施)